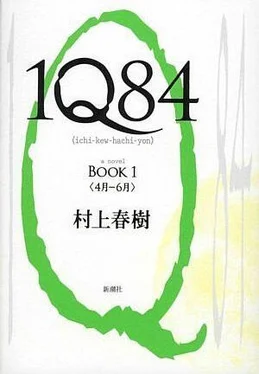「君はいつもどんな本を読んでいるの?」、天吾は退屈さに耐えかねて、電車が三鷹を過ぎたあたりでそう尋ねてみた。それはいつかふかえりに尋ねてみたいと思っていたことだった。
ふかえりは天吾をちらりと見て、それからまた顔を正面に向けた。「ホンはよまない」と彼女は簡潔に答えた。
「ぜんぜん?」
ふかえりは短く肯いた。
「本を読むことに興味がないの?」と天吾は尋ねた。
「よむのにじかんがかかる」とふかえりは言った。
「読むのに時間がかかるから本を読まない?」と天吾はよくわからず聞き返した。
ふかえりは正面を向いたままとくに返事は返さなかった。それはどうやら<���傍点>あえて否定はしない</傍点>という意思表明であるらしかった。
もちろん一般的に言って、一冊の本を読むにはそれなりの時間がかかる。テレビを見るのや、漫画を読むのとは違う。読書というのは比較的長い時間性の中で行われる継続的な営為だ。しかしふかえりの「時間がかかる」という表現には、そのような一般論とはいくぶん違うニュアンスが込められているようだった。
「時間がかかるというのは、つまり……、<���傍点>すごく</傍点>時間がかかるってこと?」と天吾は尋ねた。
「<���傍点>すごく</傍点>」とふかえりは断言した。
「普通の人より遥かに長く?」
ふかえりはこっくりと肯いた。
「じゃあ、学校でも困るんじゃないの? 授業でいろんな本を読まなくちゃならないだろうし。もしそんなに時間がかかるとしたら」
「よんでいるふりをする」と彼女はこともなげに言った。
天吾の頭のどこかで不吉なノックの音が聞こえた。そんな音はできることなら聞こえなかったことにしてやり過ごしてしまいたかったが、そういうわけにもいかない。彼は事実を知らなくてはならない。
天吾は質問した。「君が言ってるのはつまり、いわゆるディスレクシアみたいなことなのかな?」
「ディスレクシア」とふかえりは反復した。
「読字障害」
「そういわれたことはある。ディス——」
「誰に言われたの?」
その少女は小さく肩をすぼめた。
「つまり——」と天吾は手探りをするように言葉を求めた、「小さいときからずっとそうだったの?」
ふかえりは肯いた。
「ということは、これまで小説みたいなものもほとんど読んでこなかったわけだ」
「じぶんでは」とふかえりは言った。
それで彼女の書くものが、どんな作家の影響も受けていないことの説明はつく。筋の通った立派な説明だ。
「自分では読まなかった」と天吾は言った。
「だれかがよんでくれた」とふかえりは言った。
「お父さんとかお母さんが声に出して本を読んでくれた?」
ふかえりはそれには答えなかった。
「でも読めなくても、書く方は大丈夫なんだね」、天吾は恐る恐る尋ねた。
ふかえりは首を振った。「かくこともじかんがかかる」
「<���傍点>すごく</傍点>時間がかかる?」
ふかえりはまた小さく肩をすぼめた。イエスということだ。
天吾はシートの上で座り直し、身体の位置を変えた。「ということはひょっとして、『空気さなぎ』は君が自分で文章を書いたわけじゃないんだ」
「わたしはかいていない」
天吾は数秒の間を置いた。重みのある数秒間だった。「じゃあ誰が書いたの?」
「アザミ」とふかえりは言った。
「アザミって誰?」
「ふたつ<���傍点>としした</傍点>」
もう一度短い空白があった。「その子が君のかわりに『空気さなぎ』を書いた」
ふかえりはごく当り前に肯いた。
天吾は懸命に頭を働かせた。「つまり、君が物語を語って、それをアザミが文章にした。そういうこと?」
「タイプしてインサツした」とふかえりは言った。
天吾は唇を噛み、提示されたいくつかの事実を頭の中に並べ、前後左右を整えた。それから言った、「つまりアザミが、そのインサツしたものを雑誌の新人賞に応募したんだね。おそらく君には内緒で、『空気さなぎ』というタイトルをつけて」
ふかえりはイエスともノーともつかない首の傾げ方をした。しかし反論はなかった。おおむねそれで合っているということなのだろう。
「アザミというのは君の友だち?」
「いっしょにすんでいる」
「君の妹なの?」
ふかえりは首を振った。「センセイのこども」
「先生」と天吾は言った。「その<���傍点>先生</傍点>も、君と一緒に暮らしているということ?」
ふかえりは肯いた。今更どうしてそんなことを訊くのか、という風に。
「僕が今から会いに行こうとしているのが、きっとその先生なんだろうね」
ふかえりは天吾の方を向き、遠くの雲の流れを観察するような目でひとしきり彼の顔を見た。あるいは覚えの悪い犬の使いみちを考えているような目で。それから肯いた。
「わたしたちはセンセイにあいにいく」と彼女は表情を欠いた声で言った。
会話はそこでとりあえず終了した。天吾とふかえりはまたしばらく口を閉ざし、二人並んで車窓の外を眺めていた。のっぺりとした平板な土地に、これという特徴のない建物が、どこまでも際限なく立ち並んでいる。無数のテレビ?アンテナが、虫の触角のように空に向けて突き出している。そこに暮らす人々はNHKの受信料をちゃんと払っているのだろうか。日曜日には天吾は何かにつけて受信料のことを考えてしまう。そんなこと考えたくなんかないのだが、考えないわけにはいかない。
今日、このよく晴れた四月半ばの日曜日の朝に、いくつかのあまり愉快とは言い難い事実が明らかになった。まず第一にふかえりは自分で『空気さなぎ』を書いたのではない。彼女が言うことをそのまま信じるなら(信じてはいけない理由は今のところ思いつけない)、ふかえりはただ物語を語り、別の女の子がそれを文章にした。成立過程としては『古事記』とか『平家物語』といった口承文学と同じだ。その事実は天吾が『空気さなぎ』の文章に手を入れることの罪悪感をいくらか軽減してはくれたものの、全体として見れば事態をさらに——はっきり言えば抜き差しならないほど——複雑化させていた。
そして彼女は読字障害を抱えており、本をまともに読むことができない。天吾はディスレクシアについて持っている知識を整理してみた。大学で教職課程をとったときに、その障害についてレクチャーを受けた。ディスレクシアは原理的には読み書きはできる。知能は問題ないとされる。しかし読むのに時間がかかる。短い文章を読むぶんには支障はないが、それが積み重なって長いものになると、情報処理能力が追いつかなくなる。文字とその表意性が頭の中でうまく結びつかないのだ。それが一般的なディスレクシアの症状だ。原因はまだ完全には解明されていない。しかし学校のクラスの中にディスレクシアの子供が一人か二人いたとしても、決して驚くべきことではない。アインシュタインもそうだったし、エジソンもチャーリー?ミンガスもそうだった。
Читать дальше