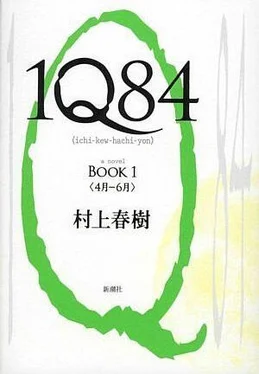天吾が感心したのは、目の見えない山羊の習性やその行動が、細かいところまで具体的に描かれているところだった。そのようなディテールが、この作品全体をとても生き生きとしたものにしている。彼女は実際に目の見えない山羊を飼ったことがあるのだろうか? そして彼女はそこに描かれているような、山中のコミューンで実際に生活していたことがあるのだろうか? たぶんあるのだろうと天吾は推測した。もしそんな経験がまったくないのだとしたら、ふかえりは物語の語り手として、それこそ希有な天性の才能を持っていることになる。
この次ふかえりに会ったとき(それは日曜日になるはずだ)、山羊とコミューンのことを尋ねてみようと天吾は思った。もちろんふかえりがそんな質問に答えてくれるかどうかはわからない。前回交わした会話を思い出すと、彼女は答えてもいいと思う質問にしか答えないように見える。答えたくない質問は、あるいは答えるつもりのない質問は、あっさり無視してしまう。まるで聞こえなかったみたいに。小松と同じだ。彼らはそういう面では似たもの同士なのだ。天吾はそうではない。何か質問されれば、それがたとえどんな質問であれ、律儀に何かしらの答えは返す。そういうのはきっと生まれつきのものなのだろう。
五時半に年上のガールフレンドから電話がかかってきた。
「今日は何をしていたの?」と彼女は尋ねた。
「一日中、ずっと小説を書いていたよ」と天吾は言った。半分は真実で、半分は嘘だ。自分の小説を書いていたわけではないのだから。でもそこまで詳しい説明をするわけにはいかない。
「仕事は捗{はかど}った?」
「まずまず」
「今日は急にごめんなさいね。来週は会えると思う」
「楽しみにしてる」と天吾は言った。
「私も」と彼女は言った。
それから彼女は子供の話をした。彼女はよく天吾を相手に子供の話をした。二人の小さな娘。天吾には兄弟もいないし、もちろん子供もいない。だから小さな子供というのがどんなものなのかよくわからない。しかし彼女はそんなことにはおかまいなく自分の子供たちの話をした。天吾は自分から多くをしゃべる方ではない。何によらずひとの話を聞くのが好きだ。だから彼女の話に興味を持って耳を傾けた。小学校二年生の長女が、学校でいじめにあっているらしいと彼女は言った。子供自身は何も言わないのだが、同級生の母親がそういうことがあるみたいだと教えてくれた。天吾はもちろんその女の子に会ったことはない。一度写真を見せてもらったことがある。母親にはあまり似ていない。
「どんなことが原因でいじめられるの?」と天吾は尋ねた。
「喘息{ぜんそく}の発作がときどき起きるから、みんなと一緒にいろんな行動ができないの。そのせいかもしれない。素直な性格の子だし、勉強の成績も悪くないんだけど」
「よくわからないな」と天吾は言った。「喘息の発作がある子供はかばわれるべきで、いじめられるべきじゃない」
「子供の世界では、そう簡単にはいかないの」と彼女は言ってため息をついた。「みんなと違うというだけでつまはじきにあうこともある。大人の世界でも似たようなものだけど、子供の世界ではそれがもっと直接的なかたちで出てくるわけ」
「具体的にどんなかたちで?」
彼女は具体的な例を並べた。ひとつひとつをとればたいしたことではないけれど、それが日常になれば子供には<���傍点>こたえる</傍点>ことだった。何かを隠す。口をきかない。意地の悪い物まねをする。
「あなたは子供のころ、いじめにあったことはある?」
天吾は子供の頃を思い出した。「ないと思う。ひょっとしたらあったのかもしれないけど、気がつかなかった」
「もし気がつかなかったのなら、それは一度もいじめにあっていないということよ。だっていじめというのは、相手に自分がいじめられていると気づかせるのがそもそもの目的なんだもの。いじめられている本人が気がつかないいじめなんて、そんなものありえない」
天吾は子供の頃から大柄だったし、力も強かった。みんなが彼に一目置いていた。いじめられなかったのはたぶんそのせいだろう。しかし当時の天吾は、いじめなんか以上に深刻な問題を抱えていた。
「君はいじめられたことはある?」と天吾は尋ねた。
「ない」と彼女ははっきり言った。そのあとに躊躇のようなものがあった。「いじめたことならあるけど」
「みんなと一緒に?」
「そう。小学校の五年生のときに。示し合わせて、男の子の一人にみんなで口をきかないようにした。なんでそんなことをしたのか、どうしても思い出せないの。何か直接の原因があったはずなんだけど、思い出せないくらいだから、そんなにたいしたことじゃなかったんじゃないかな。でもいずれにしても、そんなことをして悪かったと今では思っている。恥ずかしいことだったと思っている。どうしてそんなことしちゃったのかしら。自分でもよくわからない」
天吾はそれに関連して、ある出来事をふと思い出した。ずっと以前に起こったことだが、今でも折に触れて記憶がよみがえる。忘れることはできない。しかしその話は持ち出さなかった。話し出すと長くなる。またそれは、いったん言葉にしてしまうと、いちばん重要なニュアンスが失われてしまうという種類の出来事だった。彼はこれまでそのことを誰にも話したことがなかったし、これから先もおそらく話すことはないだろう。
「結局のところ」と年上のガールフレンドは言った、「自分が排斥されている少数の側じゃなくて、排斥している多数の側に属していることで、みんな安心できるわけ。ああ、あっちにいるのが自分じゃなくてよかったって。どんな時代でもどんな社会でも、基本的に同じことだけど、たくさんの人の側についていると、面倒なことをあまり考えずにすむ」
「少数の人の側に入ってしまうと、面倒なことばかり考えなくちゃならなくなる」
「そういうことね」と憂諺そうな声で彼女は言った。「でもそういう環境にいれば少なくとも、自分の頭が使えるようになるかもしれない」
「自分の頭を使って面倒なことばかり考えるようになるかもしれない」
「それはひとつの問題よね」
「あまり深刻に考えない方がいい」と天吾は言った。「最終的にはそれほどひどいことにはならないよ。クラスにもきっと数人は、自分の頭がまっとうに使える子供がいるはずだから」
「そうね」と彼女は言った。それからしばらく一人で何かを考えていた。天吾は受話器を耳にあてたまま、彼女の考えがまとまるのを辛抱強く待っていた。
Читать дальше