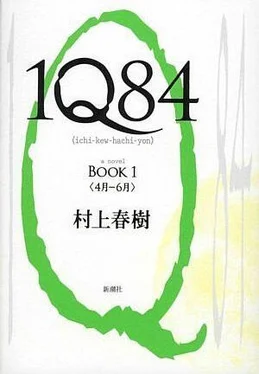息を詰めて、そのような作業を夢中になって続け、一息ついて壁の時計を見ると、もう三時前になっていた。そういえばまだ昼食をとっていない。天吾は台所に行って、やかんに湯を沸かし、そのあいだにコーヒー豆を挽いた。チーズを載せたビスケットを何枚か食べ、リンゴを噛り、湯が沸くとコーヒーを作った。それを大きなマグカップで飲みながら、気分転換のために、年上のガールフレンドとのセックスのことをひとしきり考えた。本来であれば、今頃は彼女と<���傍点>それ</傍点>をしているはずだった。そこで彼が何をするか、彼女が何をするか。彼は目を閉じ、天井に向かって、暗示と可能性を重く含んだ深いため息をついた。
それから天吾は机の前に戻り、もう一度頭の回路を切り替え、ワードプロセッサーの画面の上で、書き直された『空気さなぎ』の冒頭のブロックを読み返した。スタンリー?キューブリックの映画『突撃』の冒頭のシーンで、将軍が塹壕{ざんごう}陣地を視察して回るように。彼は自分が目にしたものに肯く。悪くない。文章は改良されている。ものごとは前進している。しかし十分とはいえない。やらなくてはならないことはまだ数多くある。あちこちで土嚢{どのう}が崩れている。機関銃の弾丸が不足している。鉄条網が手薄になっている箇所も見受けられる。
彼はその文章を紙にいったんプリントアウトした。それから文書を保存し、ワードプロセッサーの電源を切り、機械を机の脇にどかせた。そしてプリントアウトを前に置き、鉛筆を片手にもう一度念入りに読み返した。余計だと思える部分を更に削り、言い足りないと感じるところを更に書き足し、まわりに馴染まない部分を納得がいくまで書き直した。浴室の細かい隙間に合ったタイルを選ぶように、その場所に必要な言葉を慎重に選択し、いろんな角度からはまり具合を検証する。はまり具合が悪ければ、かたちを調整する。ほんのわずかなニュアンスの相違が、文章を生かしもし、損ないもする。
ワードプロセッサーの画面と、用紙に印刷されたものとでは、まったく同じ文章でも見た目の印象が微妙に違ってくる。鉛筆で紙に書くのと、ワードプロセッサーのキーボードに打ち込むのとでは、取り上げる言葉の感触が変化する。両方の角度からチェックしてみることが必要だ。機械の電源を入れ、プリントアウトに鉛筆で書き込んだ訂正箇所を、ひとつひとつ画面にフィードバックしていく。そして新しくなった原稿を今度は画面で読み直す。悪くない、と天吾は思う。それぞれの文章がしかるべき重さを持ち、そこに自然なリズムが生まれている。
天吾は椅子に座ったまま背筋を伸ばし、天井を仰ぎ、大きく息を吐いた。もちろんこれですっかり完成したわけではない。何日か置いて読み返してみれば、また手を入れるべきところが見えてくるはずだ。しかし今のところはこれでいい。このあたりが集中力の限度だ。冷却期間も必要だ。時計の針は五時に近づき、あたりはうす暗くなり始めている。明日は次のブロックを書き直そう。冒頭の数枚を書き直すだけで、ほとんど丸一日かかってしまった。思ったより手間取った。しかしいったんレールが敷かれ、リズムが生まれれば、作業はもっと迅速に運ぶはずだ。それに何によらず、いちばんむずかしくて手間がかかるのは、冒頭の部分なのだ。それさえ乗り越えてしまえば、あとは——。
それから天吾はふかえりの顔を思い浮かべ、彼女がこの書き直された原稿を読んで、いったいどのように感じるだろうと考えた。しかし彼女が何をどのように感じるか、天吾には見当もつかない。ふかえりという人間について、彼はまったく知らないも同然なのだ。彼女が十七歳で、高校三年生だが大学受験にはまったく興味を持たず、一風変わったしゃべり方をして、白ワインを好み、人の心をかき乱すような種類の美しい顔立ちをしている、という以外には何ひとつ。
しかしふかえりがこの『空気さなぎ』の中で描こうとしている(あるいは記録しようとしている)世界のあり方を、自分がおおむね正確に把握しつつあるという手応えが、あるいは手応えに近いものが、天吾の中に生まれた。ふかえりがその独特の限定された言語を用いて描こうとした光景は、天吾が丁寧に、注意深く手を入れて書き直したことによって、以前にも増して鮮やかに、明確にそこに浮かび上がっていた。そこにはひとつの流れが生まれていた。天吾にはそれがわかった。彼はあくまで技術的な側面から手を加え補強しただけなのだが、まるでもともと自分が書いたもののように、その仕上がりは自然でしつくりとしていた。そして『空気さなぎ』というひとつの物語が、そこから力強く立ち上がろうとしていた。
天吾にはそれが何より嬉しかった。書き直しの作業に長い時間意識を集中させていたせいで、体は疲弊していたが、それと裏腹に気持ちは昂揚していた。ワードプロセッサーの電源を切り、机の前を離れたあとも、このままもっと書き直しを続けていたいという思いがしばらく収まらなかった。彼はこの物語の書き直し作業を心から楽しんでいた。このぶんで行けば、ふかえりをがっかりさせないで済むかもしれない。とはいえ、ふかえりが喜んだりがっかりしたりする姿が、天吾にはうまく想像できない。それどころか、口元をほころばせたり、微かに顔を曇らせたりするところだって思い描けなかった。彼女の顔には表情というものがない。もともと感情がないから表情がないのか、それとも感情はあるがそれが表情と結びついていないのか、天吾にはわからない。とにかく不思議な少女だ、と天吾はあらためて思った。
『空気さなぎ』の主人公はおそらくは過去のふかえり自身だった。
彼女は十歳の少女で、山中にある特殊なコミューンで(あるいはコミューンに類する場所で)一匹の盲目の山羊の世話をしている。それが彼女に与えられた仕事だ。すべての子供たちはそれぞれの仕事を与えられている。その山羊は年老いてはいるがそのコミュニティーにとってとくべつな意味を持つ山羊であり、何かに損なわれないように見張っている必要がある。いっときも目を離してはならない。彼女はそう言いつけられる。しかしついうっかりして目を離し、そのあいだに山羊は死んでしまう。彼女はそのことで懲罰を受ける。古い土蔵に死んだ山羊と一緒に入れられる。その十日間、少女は完全に隔離され、外に出ることは許されない。誰かと口をきくことも許されていない。
山羊はリトル?ピープルとこの世界の通路の役をつとめている。リトル?ピープルが良き人々なのか悪しき人々なのか、彼女にはわからない(天吾にももちろんわからない)。夜になるとリトル?ピープルはこの山羊の死体を通ってこちら側の世界にやってくる。そして夜が明けるとまた向こう側に帰って行く。少女はリトル?ピープルと話をすることができる。彼らは少女に、空気さなぎの作り方を教える。
Читать дальше