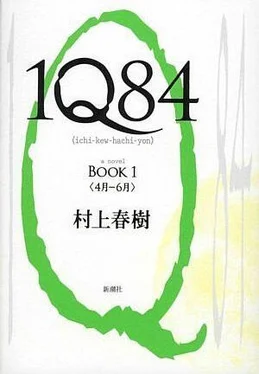目を覚ましたのは朝の八時半だった。ふかえりの姿はベッドの中にはなかった。彼が貸したパジャマは丸められて、洗面所の洗濯機の中に放り込まれていた。手首と足首のところは折られたままになっていた。台所のテーブルに書き置きがあった。メモ用紙にボールペンで「ギリヤーク人は今どうしているのか。うちに帰る」と書かれていた。字は小さく、硬く角張って、どことなく不自然に見えた。貝殻を集めて、砂浜に書かれた字を、上空から眺めているみたいな感じがあった。彼はその紙を畳んで、机の抽斗にしまった。十一時にやってくるはずのガールフレンドにそんなものを見つけられたら、きつと一騒動になる。
天吾はベッドをきれいに整え、チェーホフの労作を書棚に戻した。それからコーヒーを作り、トーストを焼いた。朝食をとりながら、自分の胸の中に何か重いものが腰を据えていることに気づいた。それが何であるかがわかるまでに時間がかかった。それはふかえりの静かな寝顔だった。
もしかして、おれはあの子に恋をしているのだろうか? いや、そんなことはない、と天吾は自分に言い聞かせた。ただ彼女の中にある何かが、たまたま物理的におれの心を揺さぶるだけだ。でもそれでは何故、彼女が身につけたパジャマのことがこうも気になるのだろう? どうして(深く意識もせずに)手にとってその匂いを嗅いでしまったのだろう?
疑問が多すぎる。「小説家とは問題を解決する人間ではない。問題を提起する人間である」と言ったのはたしかチェーホフだ。なかなかの名言だ、しかしチェーホフは作品に対してのみならず、自らの人生に対しても同じような態度で臨み続けた。そこには問題提起はあったが、解決はなかった。自分が不治の肺病を患っていると知りながら(医師だからわからないわけがない)、その事実を無視しようと努め、自分が死につつあることを実際に死の床につくまで信じなかった。激しく喀血しながら、若くして死んでいった。
天吾は首を振り、テーブルから立ち上がった。今日はガールフレンドの来る日だ。これから洗濯をして掃除をしなくてはならない。考えるのはそのあとにしよう。
第21章 青豆
どれほど遠いところに行こうと試みても
青豆は区の図書館に行き、前と同じ手順を踏んで机の上に新聞の縮刷版を広げた。三年前の秋に山梨県で起こった、過激派と警官隊とのあいだの銃撃戦についてもう一度調べるためだ。老婦人が話していた「さきがけ」という教団の本部は山梨県の山の中にあった。そしてこの銃撃戦が行われたのも、やはり山梨県の山中だった。ただの偶然の一致かもしれない。しかし偶然の一致というのが、青豆にはもうひとつ気に入らなかった。その二つのあいだには繋がりがあるかもしれない。老婦人の口にした「あんな重大な事件」という表現も、何らかの関連性を示唆しているようだった。
銃撃戦の起こったのは三年前、一九八一年(青豆の仮説によれば「1Q84年の三年前の年」ということになる)の十月十九日だ。銃撃戦の詳細については、彼女は前に図書館に来たときに報道記事を読んで、既に大まかな知識を得ていた。だから今回はその部分はざっと流し読みして、後日に出た関連記事や、事件を様々な角度から分析した記事を中心に読むことにした。
最初の銃撃戦では、中国製のカラシニコフ自動小銃によって三人の警官が射殺され、二人が重軽傷を負った。その後過激派グループは武装したまま山中に逃亡し、武装警官隊によって大がかりな山狩りが行われた。それと同時に、完全武装した自衛隊の空挺部隊がヘリコプターで送り込まれた。その結果、過激派の三人が投降を拒否して射殺され、二人が重傷を負い(一人は三日後に病院で死亡した。もう一人の重傷者がどうなったのかは、新聞記事からは判明しなかった)、四人が無傷かあるいは軽傷を負って逮捕された。高性能の防弾ベストを着用していたから、自衛隊員や警官たちには被害は出なかった。警官の一人が追跡中に崖から転落して脚を折っただけだった。過激派のうちの一人だけは行方不明のままだった。その男は大がかりな捜査にもかかわらず、どこかに消えてしまったようだ。
銃撃戦の衝撃が一段落すると、新聞はこの過激派の成立過程について詳細な報道を始めた。彼らは一九七〇年前後の大学紛争の落とし子だった。メンバーの半数以上は東大安田講堂か日大の占拠に関わっていた。彼らの「砦」が機動隊の実力行使によって陥落したあと、大学を追われたり、あるいは大学キャンパスを中心とする都市部での政治活動に行き詰まりを覚えた学生たちや一部教官が、セクトを超えて合流し、山梨県に農場を作ってコミューン活動を開始した。最初は農業を中心とするコミューンの集合体である「タカシマ塾」に参加したのだが、その生活に満足できず、メンバーを再編成して独立し、山奥の廃村を破格に安く手に入れて、そこで農業を営むようになった。初めのうちは苦労があったようだが、やがて有…機農法を用いた食材が都市部で静かなブームになり、野菜の通信販売がビジネスとして成立するようになった。そのような追い風を受けて彼らの農園はまずまず順調に発展し、規模を徐々に拡大していった。何はともあれ彼らはシリアスで勤勉な人々であり、指導者のもとによく組織化されていた。「さきがけ」というのがそのコミューンの名前だった。
青豆は顔を大きくしかめ、生唾を呑み込んだ。喉の奥で大きな音がした。それから彼女は手にしたボールペンで、机の表面をこつこつと叩いた。
彼女は記事を読み続けた。
しかし経営が安定する一方で、「さきがけ」の内部では分裂が次第に明確なかたちをとっていった。マルクシズムにのっとったゲリラ的な革命運動を希求し続けようとする過激な「武闘派」と、現在の日本においては暴力革命は現実的な選択ではないという事実を受け入れ、その上で資本主義の精神を否定し、土地と共に生きる自然な生活を追求しようとする比較的穏健な「コミューン派」に、グループが大きく二分してしまったのだ。そして一九七六年に数で優勢を誇るコミューン派が武闘派を「さきがけ」から放逐する事態に到った。
とはいえ「さきがけ」は力ずくで武闘派を追い出したわけではない。新聞によれば、彼らは武闘派に新しい替わりの土地と、ある程度の資金を提供し、円満に「お引き取り願った」らしい。武闘派はその取り引きに応じ、新しい代替地に彼ら自身のコミューン「あけぼの」をたちあげた。そしてどこかの時点で彼らは高性能の武器を入手したようだ。そのルートと資金の内容については今後の捜査による解明が待たれている。
Читать дальше