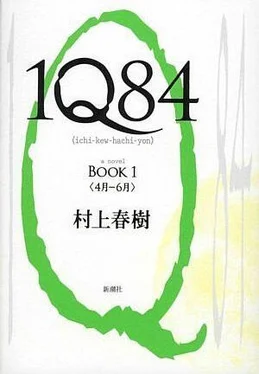一方の農業コミューン「さきがけ」がいつの時点で、どのようにして宗教団体へと方向転換していったのか、そのきっかけは何だったのか、警察にも新聞社にもよくつかめていないようだった。しかし「武闘派」をトラブルなしで切り捨てたそのコミューンは、その前後から急速に宗教的な傾向を深めたようで、一九七九年には宗教法人として認証を受けるに至った。そして周辺の土地を次々に購入し、農地と施設を拡張していった。教団施設のまわりには高い塀が築かれ、外部の人々はそこに出入りすることができなくなった。「修行の妨げになるから」というのが理由だった。そのような資金がどこから入ってくるのか、どうしてそれほど早い時期に宗教法人の認証を受けることができたのか、それも明らかにされていない部分だった。
新しい土地に移った過激派グループは、農作業と並行して敷地内での秘密武闘訓練に力を入れ、近隣の農民とのあいだにいくつかのトラブルを引き起こした。そのうちのひとつは、「あけぼの」の敷地内を流れる小さな河川の水利権をめぐる争いだった。その河川は昔から、地域の共同農業用水として使用されてきたのだが、「あけぼの」は近隣住民の敷地内への立ち入りを拒んだ。紛争は数年にわたって続き、彼らのめぐらした鉄条網の塀に対して苦情を申し出た住民が、「あけぼの」の数人のメンバーに激しく殴打されるという事件が起こるに至った。山梨県警が傷害事件として捜査令状を取り、事情聴取のために「あけぼの」に向かった。そしてそこで思いもよらず銃撃戦が持ち上がったわけだ。
山中での激しい銃撃戦の末に、「あけぼの」が事実上壊滅したあと、教団「さきがけ」は間を置かず公式な声明を発表した。ビジネス?スーツを着た、若いハンサムな教団のスポークスマンが、記者会見を開いて声明を読み上げた。論旨は明確だった。「あけぼの」と「さきがけ」とのあいだには、過去においてはともかく、現在の時点では関係は一切ない。分離したあとは、業務連絡のほかには行き来はほとんどなかった。「さきがけ」は農作業に励み、法律を遵守し、平和な精神世界を希求する共同体であり、過激な革命思想を追求する「あけぼの」派の構成員とは、これ以上行動を共にできないという結論に至り、円満に訣を分かった。その後「さきがけ」は宗教団体として、宗教法人認証も受けている。このような流血事件が引き起こされたのはまことに不幸なことではあり、殉職された警察官のみなさんとそのご家族に、深く哀悼の意を表したい。どのようなかたちにおいても、教団「さきがけ」は今回の出来事には関与していない。とはいえ「あけぼの」の出身母胎が「さきがけ」であることは打ち消しがたい事実であり、もし今回の事件に関連して、何らかのかたちで当局の調査が必要とされるのであれば、無用の誤解を招かぬためにも、教団「さきがけ」は進んでそれを受け入れる用意がある。当教団は社会に向けて開かれた合法的な団体であり、隠すべきものは何ひとつない。開示の必要な情報があれば、可能な限り要望に応じたい。
数日後、その声明にこたえるかのように、山梨県警が捜査令状を手に教団内に入り、一日かけて広い敷地をまわり、施設内部や各種書類を入念に調査した。何人かの幹部が事情聴取された。表面的に決別したとはいえ、分離後も両者のあいだには交流が続いており、「さきがけ」が「あけぼの」の活動に水面下で関与していたのではないかというのが、捜査当局の疑念だった。しかしそれらしき証拠はひとつとして見つからなかった。美しい雑木林の中の小径を縫うように木造の修行施設が点在し、そこで多くの人々が質素な修行衣を着て、瞑想や厳しい修行に励んでいるだけだ。そのかたわらで信者たちによる農耕作業がおこなわれていた。よく手入れされた農機具や重機が揃っているだけで、武器らしきものは発見できず、暴力を示唆するものも目につかなかった。すべては清潔で、整然としていた。小綺麗な食堂があり、宿泊所があり、簡単な(しかし要を得た)医療施設もあった。二階建ての図書館には数多くの仏典や仏教書が収められており、専門家による研究や翻訳が進められていた。宗教施設というよりはむしろ、こぢんまりした私立大学のキャンパスみたいに見えた。警官たちは拍子抜けして、ほとんど手ぶらで引き上げた。
その数日後、今度は新聞やテレビの取材記者が教団に招かれたが、彼らがそこで目にしたのも、警官たちが見たのとだいたい同じ風景だった。よくあるお仕着せのツアーではなく、記者たちは付き添いなしに敷地内の好きな場所を訪れて、誰とでも自由に話をし、それを記事にすることができた。ただし信者のプライバシー保護のために、教団の許可を得た映像と写真だけを使用するという取り決めが、メディアとのあいだに結ばれた。修行衣を身にまとった数人の教団幹部が、集会用の広い部屋で記者たちの質問に答え、教団の成り立ちや教義や運営方針について説明した。言葉遣いは丁寧、かつ率直だった。宗教団体によくあるプロパガンダ臭は一切排除されていた。彼らは宗教団体の幹部というよりは、プレゼンテーションに習熟した広告代理店の上級社員のように見えた。着ている服が違っているだけだ。
我々は明確な教義を持っているわけではない、と彼らは説明した。成文化されたマニュアルのようなものを、我々は必要とはしていない。我々がおこなっているのは初期仏教の原理的な研究であり、そこでおこなわれていた様々な修行の実践である。そのような具体的な実践をとおして、字義的ではない、より流動的な宗教的覚醒を得ることが、我々の目指すところである。個人個人のそのような自発的覚醒が、集合的に我々の教理を作り上げていると考えていただければいい。教義があって覚醒があるのではなく、まず個々の覚醒があり、その中から結果的に、我々の則{のり}を決定するための教義が自然発生的に生まれてくる。それが我々の基本的な方針である。そのような意味では、我々は既成宗教とは成り立ちを大きく異にしている。
資金については現在のところ、多くの宗教団体と同じように、その一部を信者の自発的な寄付に頼っている。しかし最終的には、寄付に安易に頼ることなく、農業を中心とした、自給自足の質素な生活を確立することを目標に置いている。そのような「足るを知る」生活の中で、肉体を清浄にし、精神を錬磨することによって、魂の平穏を得ることを目指している。競争社会の物質主義にむなしさを覚えた人々が、より深みのある別の座標軸を求めて、次々に教団の門をくぐっている。高い教育を受け、専門職に就き、社会的地位を得ていた人々も少なくない。我々は世間のいわゆる「新興宗教」とは一線を画している。人々の現世的な悩みを安易に引き受け、一括して人助けをするような「ファーストフード」宗教団体ではないし、そういう方向を目指しているわけでもない。弱者の救済はもちろん大事なことだが、自らを救済しようとする意識の高い人々にふさわしい場所と適切な助力を与える、いわば宗教の「大学院」に相当する施設だと考えていただければ近いかもしれない。
Читать дальше