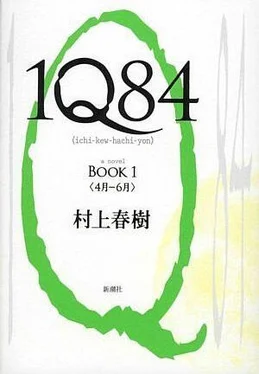タクシーの運転手にも何かしら奇妙な印象があった。彼が別れ際に口にした言葉を、青豆はまだよく覚えていた。彼女はその言葉をできる限り正確に頭の中に再現した。
そういうことをしますと、そのあとの日常の風景がいつもとは少し違って見えてくるかもしれません。でも見かけにだまされないように。現実というのは常にひとつきりです。
変わったことを言う運転手だと、青豆はそのとき思った。でも彼が何を言いたいのかよくわからなかったし、とくに深く気にはしなかった。彼女は先を急いでいたし、ややこしいことをあれこれ考えている余裕もなかった。しかし今こうして思い返してみると、その発言はいかにも唐突であり奇妙だった。忠告のようでもあり、暗示的なメッセージのようにもとれる。運転手はいったい何を私に伝えたかったのだろう?
そしてヤナーチェックの音楽。
どうしてその音楽がヤナーチェックの『シンフォニエッタ』であると、即座にわかったのだろう。それが一九二六年に作曲されたことを、私はどうして知っていたのだろう。ヤナーチェックの『シンフォニエッタ』は、冒頭のテーマを耳にすれば誰でもわかる、というようなポピュラーな音楽ではない。そして私はこれまで、とくにクラシック音楽を熱心に聴いてきたわけでもない。ハイドンとベートーヴェンの音楽の違いだってよくわからない。なのになぜ、タクシーのラジオから流れてくるその音楽を耳にして、すぐに「これはヤナーチェックの『シンフォニエッタ』だ」とわかったのだろう。そしてどうしてその音楽が、私の身体に激しい個人的な揺さぶりのようなものを与えたのだろう。
そう、それはとても<���傍点>個人的な</傍点>種類の揺さぶりだった。まるで長いあいだ眠っていた潜在記憶が、何かのきっかけで思いも寄らぬ時に呼び覚まされたような、そんな感じだった。肩を掴まれて揺すられているような感触がそこにはあった。とすれば、私はこれまでの人生のどこかの地点で、その音楽と深く関わりを持ったのかもしれない。その音楽が流れてきて、スイッチが自動的にオンになって、私の中にある何かの記憶がむくむくと覚醒したのかもしれない。ヤナーチェックの『シンフォニエッタ』。しかしどれだけ記憶の底を探っても、青豆には心当たりはなかった。
青豆はあたりを見まわし、自分の手のひらを眺め、爪のかたちを点検し、念のためにシャツの上から両手で乳房をつかんでかたちを確かめてみた。とくに変わりはない。同じ大きさとかたちだ。私はいつもの私であり、世界はいつもの世界だ。しかし何かが違い始めている。青豆にはそれが感じられた。絵の間違い探しと同じだ。ここに二つの絵がある。左右並べて壁に掛けて見比べてみても、そっくり同じ絵のように見える。しかし注意深く細部を検証していくと、いくつかの些細なものごとが異なっていることがわかる。
彼女は気持ちを切り替えて新聞の縮刷版のページを繰り、本栖湖の銃撃戦についての詳細をメモした。五挺の中国製AK47カラシニコフ自動小銃は、朝鮮半島から密輸されたものではないかと推測されていた。おそらくは軍払い下げの中古品で、程度は悪くない。弾薬もたっぷりあった。日本海の海岸線は長い。漁船に偽装された工作船を使い、夜陰にまぎれて武器弾薬を持ち込むのは、それほどむずかしいことではない。彼らはそのようにして覚醒剤と武器を日本に持ち込み、大量の日本円を持ち帰る。
山梨県警の警官たちは、過激派グループがそこまで高度に武装化されていることを知らなかった。彼らは傷害罪——あくまで名目的なものだ——で捜査令状をとり、二台のパトカーとミニバスに分乗し、通常の装備でその「あけぼの」と呼ばれるグループの本拠地である「農場」に向かった。グループのメンバーは表向きはそこで有機農法による農業を営んでいた。彼らは警察による農場の立ち入り捜査を拒否した。当然のことながら押し合いのようなかっこうになり、そして何かのきっかけで銃撃戦が始まった。
実際に使われはしなかったものの、彼らは中国製の高性能手榴弾まで用意していた。手榴弾による攻撃がなかったのは、まだ入手してから間もなく、それを使いこなす訓練が十分におこなわれていなかったからだ。それはまことに幸運なことだった。手榴弾が用いられていたら、警察や自衛隊の被害はずっと大きなものになっていたはずだから。警官たちは当初防弾チョッキの用意さえしていなかった。警察当局の情報分析の甘さと、装備の旧さが指摘された。しかし世間の人々がいちばん驚愕したのは、過激派がまだそのような実戦部隊として存続し、水面下で活発に活動していたという事実だった。六〇年代後半の派手な「革命」騒ぎは既に過去のものとなり、過激派の残党も浅間山荘事件で既に壊滅したと思われていたのだ。
青豆はすべてのメモを取り終えてから、新聞の縮刷版をカウンターに返し、音楽関係の棚から『世界の作曲家』という分厚い本を選んで、机に戻った。そしてヤナーチェックのページを開いた。
レオシュ?ヤナーチェックは一八五四年にモラヴィアの村に生まれ、一九二八年に死んだ。本には晩年の顔写真が載っていた。禿げてはおらず、頭は元気のいい野草のような白髪に覆われている。頭のかたちまではわからない。『シンフォニエッタ』は一九二六年に作曲されている。ヤナーチェックは愛のない不幸な結婚生活を送っていたが、一九一七年、六十三歳のときに人妻のカミラと出会って恋に落ちた。既婚者同士の熟年愛である。一時期スランプに悩んでいたヤナーチェックは、このカミラとの出会いを契機として、旺盛な創作欲を取り戻す。そして晩年の傑作が次々に世に問われることになる。
ある日、彼女と二人で公園を散歩しているときに、野外音楽堂で演奏会が開かれているのを見かけ、立ち止まってその演奏を聴いていた。そのときにヤナーチェックは唐突な幸福感を全身に感じて、この『シンフォニエッタ』の曲想を得た。そのとき自分の頭の中で何かがはじけたような感覚があり、鮮やかな悦惚感に包まれたと彼は述懐している。ヤナーチェックは当時たまたま大きな体育大会のためのファンファーレの作曲を依頼されており、そのファンファーレのモチーフと、公園で得た「曲想」がひとつになって『シンフォニエッタ』という作品が生まれた。「小交響曲」という名前がついているが、構成はあくまで非伝統的なものであり、金管楽器による輝かしい祝祭的なファンファーレと、中欧的なしっとりとした弦楽合奏が組み合わされ、独自の雰囲気を作りあげている——と解説にはあった。
Читать дальше