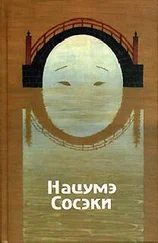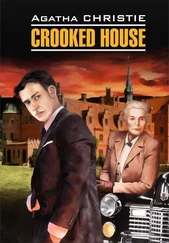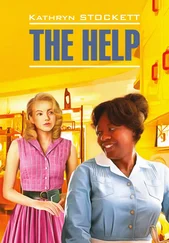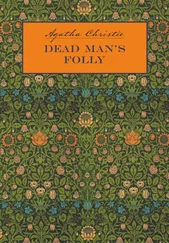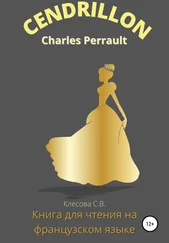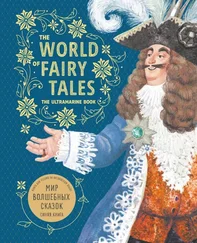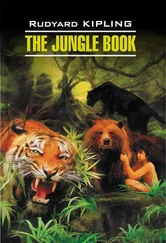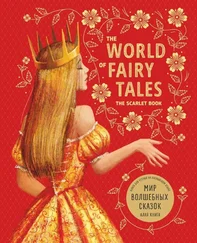「例の松た、何だい」と主人が断句《だんく》を投げ入れる。
「首懸《くびかけ》の松さ」と迷亭は領《えり》を縮める。
「首懸の松は鴻《こう》の台《だい》でしょう」寒月が波紋《はもん》をひろげる。
「鴻《こう》の台《だい》のは鐘懸《かねかけ》の松で、土手三番町のは首懸《くびかけ》の松さ。なぜこう云う名が付いたかと云うと、昔《むか》しからの言い伝えで誰でもこの松の下へ来ると首が縊《くく》りたくなる。土手の上に松は何十本となくあるが、そら首縊《くびくく》りだと来て見ると必ずこの松へぶら下がっている。年に二三|返《べん》はきっとぶら下がっている。どうしても他《ほか》の松では死ぬ気にならん。見ると、うまい具合に枝が往来の方へ横に出ている。ああ好い枝振りだ。あのままにしておくのは惜しいものだ。どうかしてあすこの所へ人間を下げて見たい、誰か来ないかしらと、四辺《あたり》を見渡すと生憎《あいにく》誰も来ない。仕方がない、自分で下がろうか知らん。いやいや自分が下がっては命がない、危《あぶ》ないからよそう。しかし昔の希臘人《ギリシャじん》は宴会の席で首縊《くびくく》りの真似をして余興を添えたと云う話しがある。一人が台の上へ登って縄の結び目へ首を入れる途端に他《ほか》のものが台を蹴返す。首を入れた当人は台を引かれると同時に縄をゆるめて飛び下りるという趣向《しゅこう》である。果してそれが事実なら別段恐るるにも及ばん、僕も一つ試みようと枝へ手を懸けて見ると好い具合に撓《しわ》る。撓り按排《あんばい》が実に美的である。首がかかってふわふわするところを想像して見ると嬉しくてたまらん。是非やる事にしようと思ったが、もし東風《とうふう》が来て待っていると気の毒だと考え出した。それではまず東風《とうふう》に逢《あ》って約束通り話しをして、それから出直そうと云う気になってついにうちへ帰ったのさ」
「それで市《いち》が栄えたのかい」と主人が聞く。
「面白いですな」と寒月がにやにやしながら云う。
「うちへ帰って見ると東風は来ていない。しかし今日《こんにち》は無拠処《よんどころなき》差支《さしつか》えがあって出られぬ、いずれ永日《えいじつ》御面晤《ごめんご》を期すという端書《はがき》があったので、やっと安心して、これなら心置きなく首が縊《くく》れる嬉しいと思った。で早速下駄を引き懸けて、急ぎ足で元の所へ引き返して見る……」と云って主人と寒月の顔を見てすましている。
「見るとどうしたんだい」と主人は少し焦《じ》れる。
「いよいよ佳境に入りますね」と寒月は羽織の紐《ひも》をひねくる。
「見ると、もう誰か来て先へぶら下がっている。たった一足違いでねえ君、残念な事をしたよ。考えると何でもその時は死神《しにがみ》に取り着かれたんだね。ゼ ムスなどに云わせると副意識下の幽冥界《ゆうめいかい》と僕が存在している現実界が一種の因果法によって互に感応《かんのう》したんだろう。実に不思議な事があるものじゃないか」迷亭はすまし返っている。
主人はまたやられたと思いながら何も云わずに空也餅《くうやもち》を頬張《ほおば》って口をもごもご云わしている。
寒月は火鉢の灰を丁寧に掻《か》き馴《な》らして、俯向《うつむ》いてにやにや笑っていたが、やがて口を開く。極めて静かな調子である。
「なるほど伺って見ると不思議な事でちょっと有りそうにも思われませんが、私などは自分でやはり似たような経験をつい近頃したものですから、少しも疑がう気になりません」
「おや君も首を縊《くく》りたくなったのかい」
「いえ私のは首じゃないんで。これもちょうど明ければ昨年の暮の事でしかも先生と同日同刻くらいに起った出来事ですからなおさら不思議に思われます」
「こりゃ面白い」と迷亭も空也餅を頬張る。
「その日は向島の知人の家《うち》で忘年会|兼《けん》合奏会がありまして、私もそれへヴァイオリンを携《たずさ》えて行きました。十五六人令嬢やら令夫人が集ってなかなか盛会で、近来の快事と思うくらいに万事が整っていました。晩餐《ばんさん》もすみ合奏もすんで四方《よも》の話しが出て時刻も大分《だいぶ》遅くなったから、もう暇乞《いとまご》いをして帰ろうかと思っていますと、某博士の夫人が私のそばへ来てあなたは○○子さんの御病気を御承知ですかと小声で聞きますので、実はその両三日前《りょうさんにちまえ》に逢った時は平常の通りどこも悪いようには見受けませんでしたから、私も驚ろいて精《くわ》しく様子を聞いて見ますと、私《わたく》しの逢ったその晩から急に発熱して、いろいろな譫語《うわごと》を絶間なく口走《くちばし》るそうで、それだけなら宜《い》いですがその譫語のうちに私の名が時々出て来るというのです」
主人は無論、迷亭先生も「御安《おやす》くないね」などという月並《つきなみ》は云わず、静粛に謹聴している。
「医者を呼んで見てもらうと、何だか病名はわからんが、何しろ熱が劇《はげ》しいので脳を犯しているから、もし睡眠剤《すいみんざい》が思うように功を奏しないと危険であると云う診断だそうで私はそれを聞くや否や一種いやな感じが起ったのです。ちょうど夢でうなされる時のような重くるしい感じで周囲の空気が急に固形体になって四方から吾が身をしめつけるごとく思われました。帰り道にもその事ばかりが頭の中にあって苦しくてたまらない。あの奇麗な、あの快活なあの健康な○○子さんが……」
「ちょっと失敬だが待ってくれ給え。さっきから伺っていると○○子さんと云うのが二|返《へん》ばかり聞えるようだが、もし差支《さしつか》えがなければ承《うけたま》わりたいね、君」と主人を顧《かえり》みると、主人も「うむ」と生返事《なまへんじ》をする。
「いやそれだけは当人の迷惑になるかも知れませんから廃《よ》しましょう」
「すべて曖々然《あいあいぜん》として昧々然《まいまいぜん》たるかたで行くつもりかね」
「冷笑なさってはいけません、極真面目《ごくまじめ》な話しなんですから……とにかくあの婦人が急にそんな病気になった事を考えると、実に飛花落葉《ひからくよう》の感慨で胸が一杯になって、総身《そうしん》の活気が一度にストライキを起したように元気がにわかに滅入《めい》ってしまいまして、ただ蹌々《そうそう》として踉々《ろうろう》という形《かた》ちで吾妻橋《あずまばし》へきかかったのです。欄干に倚《よ》って下を見ると満潮《まんちょう》か干潮《かんちょう》か分りませんが、黒い水がかたまってただ動いているように見えます。花川戸《はなかわど》の方から人力車が一台|馳《か》けて来て橋の上を通りました。その提灯《ちょうちん》の火を見送っていると、だんだん小くなって札幌《さっぽろ》ビ ルの処で消えました。私はまた水を見る。すると遥《はる》かの川上の方で私の名を呼ぶ声が聞えるのです。はてな今時分人に呼ばれる訳はないが誰だろうと水の面《おもて》をすかして見ましたが暗くて何《なん》にも分りません。気のせいに違いない早々《そうそう》帰ろうと思って一足二足あるき出すと、また微《かす》かな声で遠くから私の名を呼ぶのです。私はまた立ち留って耳を立てて聞きました。三度目に呼ばれた時には欄干に捕《つか》まっていながら膝頭《ひざがしら》ががくがく悸《ふる》え出したのです。その声は遠くの方か、川の底から出るようですが紛《まぎ》れもない○○子の声なんでしょう。私は覚えず「は い」と返事をしたのです。その返事が大きかったものですから静かな水に響いて、自分で自分の声に驚かされて、はっと周囲を見渡しました。人も犬も月も何《なん》にも見えません。その時に私はこの「夜《よる》」の中に巻き込まれて、あの声の出る所へ行きたいと云う気がむらむらと起ったのです。○○子の声がまた苦しそうに、訴えるように、救を求めるように私の耳を刺し通したので、今度は「今|直《すぐ》に行きます」と答えて欄干から半身を出して黒い水を眺めました。どうも私を呼ぶ声が浪《なみ》の下から無理に洩《も》れて来るように思われましてね。この水の下だなと思いながら私はとうとう欄干の上に乗りましたよ。今度呼んだら飛び込もうと決心して流を見つめているとまた憐れな声が糸のように浮いて来る。ここだと思って力を込めて一反《いったん》飛び上がっておいて、そして小石か何ぞのように未練なく落ちてしまいました」
Читать дальше